道徳授業の定石化 「教科書」という権威に騙されるな。「きつねとお地蔵様」
誰が言ったか?で人は騙される。
動画の中で(2分13秒〜)、石川正三郎校長の「お地蔵さんときつね」の話が出てくる。
「辛口『向山洋一論』」P76に次のような記述がある。
本校の教育はまだまだだと思い、
「また三月になったらこの話するからよく考えておいてね。」
といって台をおりた。
おそらく新学期始まった頃の朝会での話だと推測される。
石川校長は、
「お地蔵様を受け持ちの先生と考え、きつねとうさぎを自分たちと考え、どちらの考えに賛成するか。」と質問してみた。ほとんどの児童はお地蔵様の考えに賛成であった。(前出書)
「3年の学級経営(新卒どん尻教師はガキ大将)」にはこの場面について、
「私は血の気がひいてきた。『やられた』と思った。反論の余地のない敗北感を私は感じた。石川正三郎氏の授業のレベルまで子供たちをきたえている学級は皆無だった。いや、この話が、石川正三郎氏が全教師にさりげなく仕掛けた挑戦なのだと気がついた教師は極く少数なのである。」
と記されている。
なぜ向山氏は「血の気がひ」き、「やられた」と思い、「反論の余地のない敗北感」を感じたのか。
「権威で人を判断してはいけない。」
子どもの立場になってみれば、「お地蔵様を受け持ちの先生と考え」なさいと校長先生が言っているのだから、「受け持ちの先生の言うことをしっかり聞いて学習しなさい」、と校長先生は言いたいんだろうな、と思うのが普通だ。
だが、石川校長の思いは逆だったようだ。
つまり、そんな人間に育ててはいけない。大本営の発表を正しいと信じたが故に、先の大戦で日本は多くの人命を失ったのだ。
これからの日本は、お地蔵様の言うことだからと信用し、ほんとに正しいことなのか考えもしないでありがたがるだけではなく、
「わたしもうさぎさんのように、速く走れる足がほしいのです。」
と言える子に育てていかなければならない。
石川校長は常日頃から、職員に「ぜひ、教師を批判できるような子供を育ててほしいし、その批判にきちんと応えられる教師であってほしい。」と語っていたという。だからこそ、それに応えるべく実践を積み重ねてきたであろう職員は、口先だけでなく、石川校長からの挑戦状とも言える「お地蔵様ときつねの授業」での子どもたちが示した事実を率直に受け止め、三月に向けて研鑽を積み上げていかなければならない、と気づくべきだった。だが、
「これは、校長から教師たちに突きつけられた挑戦状なのだ!」
と大森四小職員集団で気付いたのは、向山氏ただ一人だけだった。
そのように考えれば、「血の気がひ」き、「やられた」と思い、「反論の余地のない敗北感」を感じた理由も合点がいく。
「教科書は正しいか?」
道徳教科書で扱う教材も同じこと。
たとえば「金のおの」(光村1年)は、「正直」について考えるのに適した教材ということで多くの教科書に掲載されている。
「誰が一番悪いですか?」と定石発問で尋ねるなら、「友達の木こり」が一番悪いと答える子が多数を占めるだろう。まぁそれはいいとして、さらに「もういないですか?」と突っ込んで問うと、「いない」と答えて終了となってしまうのが普通だ。
だが、中には「神様が一番悪い」と考えている子もいるだろう。なぜなら神様は木こりに嘘をつくよう試した(誘惑した)上で、はじめの木こりには金の斧も銀の斧も一緒に渡し、友達の木こりからには斧を返さずに取り上げてしまった。そのやり方はどうなのか?やり過ぎではないか?
そうしたことを「正直に言える」授業をこそ教師はすべきなのではないか。
「ふたりのゆうた」(日文1年)も同じ構造になっている。一番悪いのは、躾けられていない子どもを注意をしない大人なのだが、1年生にそのことを気づかせるのは難しい。そこで、教科書の挿絵の場面毎に「自分の家では、どのように言われているのか?」少人数グループの中で出し合わせていく。すると、家でほったらかされて育ってきた子は、「なぜ、自分の家では何も言ってくれないのだろう?」と思うようになるかもしれない。
「神様が悪い、と言う考えもあるね」「注意しない大人が悪いね」という幅のある考えを持って教科書に出ている教材を読み、授業したいものだ。
「にちようびのできごと」出てこない登場人物は誰か?についてはこちら
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ




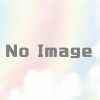



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません