夏休み前の一仕事〜未完成の作品は、一緒に作って持ち帰らせる。答えを持たせて写させる。
未完成の作品は、教師が作って持ち帰らせる。
夏休みまであと2週間。
「少しずつ荷物を持ち帰らせるのが大切だよ。」
この程度は先輩諸氏が教えてくれる。
教室内を改めて見ると、作品が未完成のまま放置されている。
はさみやのりなどが一緒に放置されている事も多いので、誰の作品なのかを特定する。
「忘れず、今週中に持ち帰りなさいよ!」
個別に声を掛けても持ち帰らない可能性が高い。未完成なのは本人が百も承知だ。自分のものだと分からないように処分したい。できるならゴミ箱に直行させてなかったことにしたい。
そこで一言。
「これ、持ち帰る前に、もう少し作ってもいい?」
持ち帰ってもはずかしくない程度まで、教師が手を入れて完成させるわけだ。
例えばパーツがばらばらになっている立体作品なら、接着剤や両面テープを使って骨組みを教師が作ってやる。手先が不器用なのでパーツとパーツをうまい具合に接合できない。言葉で説明したところですぐにできるようにならない。お金を出して買わせた作品キットを使って作らせたものなら、ある程度完成した状態での持ち帰らせれば、それを保護者が目にした際に、ある程度の納得が得られるであろう。
テスト直しは、答えを渡して写させる。
テストやドリル類もそうだ。
答えがまちがったまま、直しもさせずに持ち帰らせるのは相当に罪深い。
ドリルの答えを渡し、自分で丸を付けさせればいい。まちがった箇所はその場で直答えを見て写させればいい。それが学習というものだ。できなかった所が分かって、正しく直せば、同じ問題が次に出たときに答えられる可能性が高くなる。まちがったらまた直せばいい。
日々の学習は、受験ではないのだ。
答えを見てそっくりそのまま正しく写す。お手本を見てまねをする。「視写」「模写」の力を教室で付けてやることが初等教育6年間では最も大事な学習なのだ。
いわゆる「宿題」プリントを出すのなら、答えを裏に印刷しておいて、それを見て写させればいい。もちろん答えを見ないで書ける子もいるだろう。それはそれでいい。答えを見て自分で丸をして提出させればいい。そう考えるなら、空欄のマスに漢字を書かせる学習は宿題に向かない。お手本をなぞる欄を数回分作り、最後に何も書かれていない空欄を1回か2回埋めさせるような漢字プリントを用意すべきだ。
「子供に好かれる」教師は、連休明けも大丈夫!はこちらから。
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ





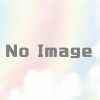


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません