道徳授業の定石化「ぼくは「のび太」でした」(東書2年)希望と勇気、努力と強い意志
どうします?扱いに悩む教材…
道徳教科書教材には、
「これ、どうやって授業するの?」
と言いたくなるものがある。
例えば今回の教材。ドラえもんで有名な藤子F・不二雄氏のマンガ家人生を取り上げた話。4ページの内、1ページ目は藤子氏とドラえもんが半分を占め、文章は3文。2〜3ページ目はまんがと写真が半分を占め、文は9文。4ページ目はドラえもんとのび太のイラストで埋められている。とにかく文章記述が少ない。読むだけではあっという間におわり、何が何だか分からない授業になりかねない。
そこで、「クイズ形式」で発問を作り、子どもとのやり取りを増やすことで、文章に書かれてない部分を補いつつ、丁寧に読み取るようにする。
あらすじ
藤子・F・不二雄先生は、子供の頃からマンガを書くのが大好きで、あこがれの手塚治虫先生の本を一ヶ月も描き写したこともあった。高校を出てから手塚先生に会いに行くと、マンガ家になるのは○○○○だと思うようになった。その後、ずっとマンガを描いてきた藤子先生は、子どもの頃「のび太」のように不器用なぼくがマンガをかき続けてきたのは、やはり◯◯◯◯なこと」と言っている。
定石①「登場人物」「セリフ」「したこと」の確定
「登場人物」「セリフ」「人物評価」の確定をする。
イラストと写真が大半を占めている教材なので、登場人物やセリフにわざわざマーカーや番号を付ける作業はいらない。
次に発問①〜③で人物評価をするが、
①「誰がいい人ですか?」
②「誰が一番だめか?」
③「誰に問題がありますか?」
と問えるほどの中身がある教材ではない。登場人物は藤子氏と手塚治虫先生だけ。どちらが「いい人か?」と問われて答えるのであれば、漫画をかく仕事は大変だなあと分からせてくれた手塚氏だろうか?
「誰が一番だめか?」の問いも、「だめな人はいない。」となるが、その理由を問えば、藤子氏は「うまくかけるようになりたいとがんばりました。」「よくこれだけかきつづけてこられた」ことを「やはりたいへんなこと」と自己評価しているので、だめなことはしていない、ということになる。
定石②変換点の検討
変換点の検討は、次の4つの発問群を使う。
④「どこから変わった?」
⑤「前はどういう状態?」
⑥「後はどういう状態?」
発問1 藤子先生の考えが変わったところはどこか。
→「まんがをかくしごとは、たいへんだなあ」
発問2 まんが家になる前はどうだったか。
→まんがをかくことが、なによりも大すき。
発問3 まんが家になった後は?
→描き続けることがたいへん。
定石③自分に返す
「自分に返す」定番発問は、次の5つ。
⑦「自分はどっちですか?」
⑧「今の自分は、前か後か?」
⑨「これからどうなりたいのか?」
⑩「そういう体験はないか?」
⑪「そういうお話を知らないか?聞いたことがないか?」
発問4 頑張っている事に取り組む時、どちらの気持ちに近いか。
発問5 これからどうなりたいか。
発問6 藤子先生のような事を思った体験はないか?
発問7 何かを頑張って長く続けている人の事を知ってたり、聞いたりしたことがないか。
まとめ
例によって、教材末尾の余白に自分の考えたことを「わ・き・お」形式で書かせ提出させる。教師の講話のバリエーションを増やす方法として、「好きこそ物の上手なれ」など「ことわざ」を紹介して終わるのもいいかもしれない。
道徳授業の定石化「七つのほし」はこちらから。
道徳授業の定石化「①登場人物の確定」「②変換点の検討」「③今と未来の選択」についてはこちらから。
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ




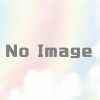


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません