「モデリング・ナンバリング・ネーミング」誰でもできる討論授業1
鉛筆1本で授業?
「伴先生、『鉛筆』で授業をする、って聞いたことあるんだけど。『ナンバリング』とかだっけ…」
某セミナーのあと、食事を共にしたS先生がこんな事を言っていた。わたしもその場で「鉛筆でも何でもいいんだけど、たとえばここにあるスプーンでも授業ができるんですよ。」とさわりをだけ紹介した。
もちろん【授業の百科事典】にもいくつか載っている。こちらが本家本元「モデリング」理論の提唱者。こちらを見てもらった方がまちがいない。
<モデリング>
「ここに鉛筆があります。」
「他にどんな鉛筆がありますか?」→指名する(色鉛筆)
「色鉛筆。そうですね。黒板に、縦書きで、色鉛筆、って書いて。」
「他にどんな鉛筆がありますか?」(長い鉛筆)→「(黒板に)書いて」
このように「問いと答えと反応の仕方」といった「一連の学習活動手順を示す」ことを「モデリング」(お手本)と言う。
<ナンバリング>
色鉛筆、長い鉛筆、短い鉛筆、赤鉛筆、青鉛筆……など、黒板にずらーっと書かれたたくさんの「鉛筆」の名前に、番号を付けること。そうすることにより、何について発言をしているのか明確になる。
<ネーミング>
いわゆる「発問」と考えても良い。良い発問なら、その後の学習活動は活性化する。ダメなら、停滞する。
授業の最初に鉛筆を提示し、「他にどんな鉛筆がありますか?」と訊いているた、一般的にはこれも「発問」という言い方をする。
ネーミングの場合、ナンバリングされた学習者からの反応を使って、どのようにするのか?を規定する問いなので、授業開始時点で出されている「発問」とは若干ニュアンスが異なる。学習のお膳立て(ネタの提示→反応の整理)がなされた状態で出される「学習問題的発問」とでも言えばいいのかもしれない。
黒板には、反応が文字列で並んでいる。それを使って学習をするとなれば、「分類」作業を促す発問が考えられる。
代表的な発問として、
①「どれが一番おかしい(変、悪い、だめ)ですか?」
②「どれが一番いいですか」
という「ベスト・ワースト」を考えさせる発問。
③「次にだめ(いい)のはどれ?」
④「二つに分けるとしたら、どれとどれですか」
⑤「どれにも当てはまらない『その他』はどれ?」
挙手させ、その数を記録し、そう考えた理由を少数意見から述べさせていく。
ここまでできれば、ありきたりの発問でするのとは一線を画した「授業」となっている。
鉛筆一本で「討論」の授業へ
理由を言わせたら、
⑥「質問がある人?」
⑦「反対意見がある人は、立って『◯◯さんに言います。」と反対意見を、相手に伝わるように優しく、ていねいな言葉遣いで言います。」
⑧「それに対して反論があれば、立って言います。」
⑨「いろいろな人の意見を聞いて考えを深めてほしいので、できるだけたくさんの人が言えるよう、同じ人が何度も言わないよう、譲り合って言います。」
「考えを変える場合、『考えを変えます。』と言って下さい。そのわけを言えるとなお良いですね。』
⑩「言う人がいなくなったり、みんな考えを変えたりしたりして、意見が出尽くしたら、その討論は終わり。次の意見の討論をします。」
ここまでできれば、いままでとは違う、手応えのある「討論」授業になっているはず。
「つまらない授業よ、サヨウナラ!」
「モデリング・ナンバリング・ネーミング」誰でもできる討論授業2」はこちらから。
道徳授業の定石化「①登場人物の確定」「②変換点の検討」「③今と未来の選択」についてはこちら
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ

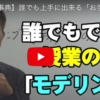
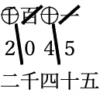

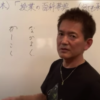


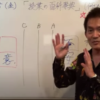
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません