道徳授業の定石化「花さき山」(教出3年)感動、畏敬の念 〔心の美しさ〕の考え方
「感動・畏敬の念」を扱うのに最適な教材?
「感動・畏敬の念」を扱う教材は、低学年では「七つのほし」「しあわせの王子」高学年では「青の洞門」が複数の教科書で収録されている。
「花さき山」も、先入観なしで読めば「いいお話ですね。」という感想が出てくるだろう。
「やさしいことをひとつすれば、ひとつさく」
「主題は何か?」と問われれば、「やさしさ」だとか、「自己犠牲」だとかという事になってくるのだろう。しかしそれをもって「感動」「畏敬の念」と繋げるのは強引すぎる。それでもなんと全6社で採択されているのだから、よほどこの内容を扱うには適した教材と判断されているのだろう。
定石発問で組み立てる
人物評価
①「誰がいい人か?」
→あや=妹のために服を買ってもらうのを我慢した。
→あんちゃん=弟のために甘えたいのを我慢している。
→やまんば=あやに「優しいことを一つすると一つ花が咲く」ことを教えてくれた。
変換点の検討
②「どこで話が変わっているか?」
あやが山で道に迷ってやまんばに会った所から。
③会う前はどんな子か?
→優しい。我慢強い。兄弟姉妹思い。
④会った後は?
→より優しくなった。
自分と比べる
⑤今の自分は、山姥に会う前のあや、会った後のあや、どちらに近いか。
⑥似たような事があったり、知っていたり聞いたりしたことはないか。
⑦これからの自分は、どちらになりたいか。
終末をどうするか
「道徳は、最後、押しつけになってはいけない」と、よく言われる。
⑥の部分をどれだけ引き出すかで、いい感じで授業が終わるかどうかが決まるだろう。そのためには、少人数グループで話し合わせるのも一つの方法だ。鍛えられている学級ならば、指名なしでの意見発表も可能だろう。この辺りは、普段の学級での授業運営次第とも言える。
あまり意見が出ないようなら、いつものことだが、教師の話をしてさらっと終わらせる。
もし子どもたちから出されていた意見が「我慢が大事」のような話になっていたのだとしたら、教師講話の中で「先生は、こんなこと「も」思いました」という形で、
「よりやさしく。より我慢強く。より兄弟姉妹を思う。そういう心のありようを『美しい』と言う人もいます。」
と修正してやるのもいいかもしれない。
「モデリング・ナンバリング・ネーミング」誰でもできる討論授業2ついてはこちら
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ






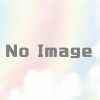

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません