「追い読み」指導は、教育活動全ての基本だ。「ドラゴン桜」に見る「追い読み」技術
「なぜ学校でやらない?」
「音読」を宿題にしている教師は多い。
一方で、教室で「追い読み」指導をやらない先生も多い。
「うそでしょう?」と思うかも知れないが、ほんとうのことだ。
初任研担当教員を務めた際、授業開始直後の指導を見てきた。大学出たての初任者は、国語の時間、何をすればいいのか戸惑いつつ、とりあえず「範読」しながら最後まで読み聞かせをする。
最後まで読み聞かせた所で、次に何をしたらいいのか分からず、指導書を取り出し、初発の感想などを言わせたり書かせたりする初任者もいる。センスがいい初任者だと、いわゆる「追い読み」をさせる。先生が最初の句点(読点)まで読んで、同じ所を復唱させるわけだ。それを教材の最後まで、延々とやり続ける。子どもは飽きてくるが、最初なので教師に付き合ってくれる。
さて次の国語の時間、どうするか?さすがに範読はない。読む範囲を限定し、「追い読み」をすべきなのだが、まずやらない。「誰か読んでくれる人?」と尋ね、さっと手を挙げた子を指名し、読んでもらう「指名読み」を行ったあと、「どんな学習をしていきたいのか?」について、発表させるなどする。
こんなふうに学習を進めていくとどうなるか?
「できる子とできない子の差が拡大していく」
音読できる子は、指名読みの際に手を挙げ、褒められてどんどん自信を付けていく。自信のない子は手を挙げないから力がつかない。いきなり指名されようものなら、不意を突かれた影響で上手に読めず、自信をなくしていく。
学校で自信を付けた子は、家に帰っての音読宿題も嬉々として取り組む。親もそれを聞いて褒める。学校で上手に読めなかった子は、音読チェック表も見せず、サイン欄に自分がもっているハンコを押して提出するわけだ。
そもそも「音読指導」を学校でやっていないのだから、家に帰ってもやるはずがない、となぜ考えないのだろう?特に学力低位の子たち。
様々な理由があっての低学力だ。家庭で音読を見てもらえない現実がある。保護者の養育態度にも問題があるのだが、それを非難していてもしょうがない。
いくら「音読を宿題」にしたところで、やってほしい子ほど家では音読できる環境がないのだから、差は拡大するだけだ。
ならば授業時間に音読をする時間を確保し、力をつけて家に帰すしか選択肢はない。
その事に一日も早く初任者は気づくべきだ。
「ドラゴン桜」にも同じ場面が
「ドラゴン桜」に「リスニング対策は追い読みで」(9巻81限目)というエピソードがある。
英語を漫然と聞き流しているだけではリスニング力は向上しない。力をつけるには、英語の「リズムとテンポ」を身に付けることが大事。そのためには、
①ビートルズやカーペンターズのような、聞き取りやすく平易な単語が使われている英語の歌を曲に合わせて歌う。
②「書いてある英文」を手元に置き、それを上手に読める人(先生)がお手本になって読み上げ、それを聞いたらすぐに声に出し、抑揚やスピードまでそっくりそのまま言えるようになるまで繰り返す。
という二つの方法を紹介している。
小学校の国語学習は、日常会話ができるから大丈夫とはならない。書いてあることを正しく理解するためには、まずは正しくすらすらと声に出して読むこと。それなしで内容を正しく理解できるということはあり得ない。ならば低学年であろうと高学年であろうと、いや、中学生、高校生、受験生まで含め、指導者は授業の中で「音読」する学習活動を取り入れる方がいい。
どれくらいやればいいかは、学年や子どもたちの実態にもよるが、基準は「正しくすらすらと」読めるようになること。低学年であれば、読む分量を区切って毎時間「追い読み」を行う。3〜4名の小グループで、「句点交代リレー読み」をするのもいい。
45分の時間配分で言うと、最初の3時間目までは15〜20分を追い読み。それ以降は、グループで15分程度。学習の後半以降は「一人読み」も含めて5〜10分は音読学習に充てる。1ヶ月行うだけで前年度までと比べものにならない位に上達する子が出てくる。そうした子をみんなの前で一人読みさせ、褒める。すると連鎖反応が広がり、夏休みになる頃には、学級の大多数の子たちが見違えるような上達ぶりを見せるようになる。
「有料セミナー級音読技術」についてはこちら
「初任者がまず身に付けるべき音読技術」についてはこちら
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ

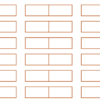

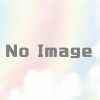


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません