「図画工作科」の授業技術 まずは一つ!指導技術を身に付ければ授業が楽しくなる。
得意技を持とう!
「図画工作科の指導に自信が持てない。」という人は少なからずいる。そういう人にお勧めなのが、「キミ子方式」と「酒井式」と呼ばれる絵画指導法だ。
的外れな批判をする人もいるが、そういう人はもともと絵画に自信がある人だ。そういう人たちが「思った通りに絵が描けないから図工はきらい!」と困っている子に対して、このような指導をしたらこんなすてきな絵が描けるようになりましたよ、と事実を示して答えを出しているのを見聞きしたことがない。
その一方で、キミ子方式なり酒井式を少しでもやってみれば分かる。「あ、これならできそう。」そう思ったなら、あとは自分の直感を信じて学ぶのみ。「いや、おかしいな。」と思えば、別の方法を模索すればいい。
どちらの方法も「『先生が子どもの絵とはこうあるのが良いと想定した絵』を描かせるために、子どもに指示を与えて『描かせる』方法」ではないことが、分かる人には分かるはずだ。
三原色・キミ子方式
超有名な絵画指導法。ヨッシーも新卒時に学んだ。
ここではリンクのみ紹介する。黒い画用紙ともやし、絵筆とパレットがあれば、自宅で描くことができる。描いた瞬間「おもしろい!」と思ったなら、講習会や「仮説実験授業」の研修会に申し込んでみるといいかもしれない。
酒井式との決定的な違いは、「輪郭線」を描かせないこと。横山大観の「朦朧体」による絵画のイメージだ。
酒井式描画指導法
作品が全てを物語る。こうした絵が嫌いな人はやらなければいい。どの子も同じレベルで、楽しそうに描いている姿を見れば、一度は酒井式指導法に挑戦してみるのも悪くないと思う。
(おまけ)
ChatGPTに、酒井式描画指導法を批判する人に対する反論を書かせてみたところ、次のような回答があったので紹介しておく。
【反論】「描かせている」のではなく、「描けるように導いている」
酒井式描画法は、単に子どもに絵を「描かせる」ことを目的としているのではなく、子どもが「描きたいものを、描けるようにする力」を育てることを目的としています。つまり、「表現の自由を奪う」のではなく、「表現する力を与える」ための指導法なのです。
■ 具体例:人物画が苦手だった子どもの変化
ある小学校の授業では、「運動会の思い出を描こう」という課題が出されました。従来の自由描画では、多くの子が「棒人間」や「顔だけの絵」にとどまっていました。ところが、酒井式で「人の顔を丸ではなく、立体的にとらえる方法」「腕や足の関節の動きの描き方」など、段階的な描画の手順を学んだことで、子どもたちは「走っている自分」「応援している家族」など、より具体的で生き生きとした場面を描けるようになりました。
この変化は、子どもたちの「個性を消した結果」ではなく、むしろ「個性を表現できる力が育った結果」です。
■ 指導=表現の枠組みを与えること
たとえば音楽教育においても、楽器の演奏技術や音階の理解を学ばせることは、「個性を奪う行為」ではありません。それはむしろ、子どもが自分の音楽を表現できる「土台」を築くためのものです。絵も同様で、構図のとり方やモチーフの描き方を学ぶことは、創造性の妨げではなく、創造性を支える「技術」です。
■ 表現の幅が広がった具体例
酒井式を学んだ子どもたちは、最初は先生の指導に沿って描きますが、次第に自分なりのアレンジを加えるようになります。例えば、ある子は「花火大会の絵」を描くときに、習った夜空の描き方に加えて、自分なりの工夫で「観客のリアクション」や「出店の明かり」を描き込み、オリジナリティ溢れる作品に仕上げました。
このように、酒井式は「型にはめる」のではなく、「表現の基礎を整え、子どもが自分で表現できる土台を築く」ための方法です。
【まとめ】
酒井式描画法は、子どもの創造性や個性を奪うものではなく、それらを「引き出す」ための具体的で実践的な方法です。指導の意図は「描かせること」ではなく、「描けるようにすること」。その成果は、子どもたちがより豊かに、自由に、自信を持って表現する姿に現れています。
批判者には、実際の子どもたちの作品の変化や、絵を描くことへの意欲の高まりを見てもらうことで、この点の理解を深めてもらえるでしょう。
なるほど!
名前を覚える〜始業式までの最優先事項 子どもの名前を覚える効果は絶大だ はこちらから。
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ


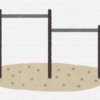


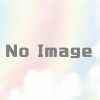
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません