授業が遅れていく…どうすればいい?授業中に扱うのが無理な観察や実験
天気に負けない理科
授業準備ができない。教材研究が間に合わない。そうしたことはよくある。特に初任者や育児に忙しい先生。こういう時に役に立つのが「授業の百科事典」。
ここでは理科授業で授業中にできない観察や実験をどうするか?について答えている。
教科書に書いてあるのを写せばいい
たったこれだけのこと。これができれば最低限をクリアしている。
予定通りに進まないのが理科。
実験や観察をどうしてもさせなければいけないものはある。だが、その日にできなければ仕方ない。
そういう時は、取りあえず「やった」として、「まとめ」をすればいい。覚えなければいけないことは「書いてまとめる」という部分は済ませておく。
理科(科学)は、本来、たくさんの観察や実験を行って記録を取り、その結果から「法則」性を帰納的に問題を解決していく学問だ。だが、教科書に書いてあることを何から何まで全部問題解決的にやって、その結果から法則性を発見するというような事をやっているわけには行かない。授業が何時間あっても終わらなくなってしまう。
実際には、「あたたかくなると、植物は芽が出て、大きくなっていく」という「法則」性を、校庭に出て観察し、「やっぱりそうだ。どの植物も芽が出て、大きくなっている。」ということを確認する学習が行われる。
観察を伴う学習はとりわけ天気に左右される。種子や苗などがまだ届かない等、さまざまな理由で準備できていない事を理由に授業進度を遅らせてしまいがちだが、そこはぐっと我慢。種まきや観察は後回しにして、ノートには「あたたかくなると、植物は芽が出て、大きくなっていく。」と教科書に「まとめ」として書かれているところを板書し、ノートに写させる。テストの穴埋めで出てきそうな「芽」「大きく」という言葉は赤で板書し、ノートに赤鉛筆で書かせる。
そのようにしてとにかく予定通り授業を進める。新学期だとゴールデンウィークまでに最初の単元をテストを含めて終わらせておきたい。
そうするためには、教科書を読み、動画を活用し、結果をノートに写す。
これに尽きる。
4年生の理科を楽しく 「授業の百科事典」でリストを作成しよう!はこちらから。
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ






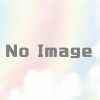

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません