「評価・評定」をどうするか。適当でいい。見ていればわかる。きっちり線引きしない。受験じゃない。
観点は2つあれば十分
7月に、次期指導要領改訂に合わせて3観点だったものを2観点に改める旨の新聞報道があった。
「主体的に学習に取り組む態度」なんてものは測定のしようがないから、「基礎・基本」と「思考・判断・表現」にAがつかない子の中で、「一生懸命学習に取り組んでるなぁ」と感じられる子に「Aをあげて、やる気を出してもらおうかな〜」という感じでつけていた先生も少なくないと思う。
2観点に減らすのはとってもいいことだと思う。これが「受験」の内申書に関わるようであれば別だが、小学校の場合、ほぼ関係ない。関係ないんだったら、あとはどうやって「やる気を引き出す」か?Educationはラテン語Educatio(引き出す)が語源となっている。How do you Educatio Possibilities of Students ?〜先生、どうやって子供達の可能性を引き出すの?と問われるということだ。
指導したことは評定できる。
指導したことは評価できる。
たとえば図工。「赤、青、黄の3色を混ぜて色を作る」という学習課題だとしよう。
パレットに3色の絵の具を出し、2色ずつ混ぜて色を作る。次に3色混ぜて色と作る。指示通りできれば「知識・技能」はB。全然違うことをやっていればC。「知識・技能」はまずBかCでふるいをかける。
さらに「水を減らしたり、増やしたりして色の濃淡を加減して着色する」ように指導したなら、だいたいそうなっていれば「思考・判断・表現」はB。できてなければC。とっても上手に着色できていればA。
最後に「かき氷」カップを印刷した画用紙に、学習したことを使ってかき氷を描いた作品を見せ、まねしてやってみるよう指示する。上手に描ければA。ぐしゃぐしゃに描いたり、それらしく描けなければC。
「主体的に」取り組んでいたかどうかまで授業中に評定できる余裕などない。
「評価・評定」の実際は、最後に提出された作品をぱっと見て、
指導したことを使って描いているなぁ、と教師が思えば「知識・技能」A。大体できていればB。やってなければC。
次に「思考・判断・表現」力を発揮して、上手に、きれいに、丁寧に描いてあるとわかる箇所が表れていればAAかABになる。
AAならばそれに伴って「主体性」はAになるだろうから、AAA。ABの子はAAの子に及ばないのだから、ABB。ABAとは付けにくい。
3原色を使って混色し、水加減を調整して描くという「知識・技能」が大体できていればB。それにも増して「思考・判断・表現」力を思う存分発揮して、上手に、きれいに、丁寧に描いた作品に仕上がっているならBAだが、それは稀。
「知識・技能」がBなら、ほとんど「思考・判断・表現」もB。よってBBが学級の5割以上。AAは3割。
これを受けて「主体的」に取り組んだかどうかの評価を付け加えると、AAAは最大2割。BBBが5割。それ以外が3割。
こんな具合に細かく評定を分ける基準を決めて作品を見ていくのだが、結局は「パッと見て」AA,AB,BBの判断は付くようになるし、「説明もしてほしい」と言われればできるだろう。
成績一覧表でにAAA、BBBと記入する際、単元ごとに観点別に点数化して付ける人もいる。
だが、作品を提出するまでの何時間かの取り組みを見てた上で、「Cは付けても1個くらい」とするなら、CBBかBCBかBBCのどれかひとつ。
①やり方が理解できず、支援や手助けがないと活動に取り組めない→CBB
②いろいろ試して取り組んでみるが、雑に仕上げてしまう→BCB
③やっている途中で集中が切れ、じゃまをしたり勝手なことをする→BBC
これにあてはまらなければBBB。これが5割いる。
AAかBAかは、作品を見たらわかる。あとはAを1つにするか2つにするか。
④課題にまじめに丁寧に努力して取り組んだ痕がある→ABAかABB
⑤構図や技法に工夫が見られる→BAAかBAB
前年度の成績と比較して調整する
最終的には、ある程度の数、作品を見ていると判断が付くようになる。
大事なのは、前学期との評定の差が大きくならないようにチェックして加減する。
AAAだった子をBBBにするわけにはいくまい。BAAにするかABAにするかAABにするか。匙加減は絶対必要だ。
そのためには、提出締切日の少し前には見直しできるように仕事や授業を進めておきたい。
評価・評定(通信簿)の考え方 テストだけで評価しない。はこちらから。
成績処理は「技術」の問題はこちらから
新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ



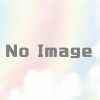


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません