常識の幅を広げる。「読書」は「嘘を見抜く力」を身につけてくれる最強ツールだ。
読書のススメ
まずは伴氏の動画を見てほしい。この話、知っていただろうか?
北村弁護士は言う。
「自民党の全議員が知っている」「大変有名な話」だという。
伴氏もそうだが、向山氏の知識量も圧倒的だった。その多くは「読書」から来ている。伴氏の有料配信に「読書クラブ」がある。何度か配信を受けたが、ほんとに知らない情報が多く、刺激になる。
教師のススメ
教師という仕事の不人気ぶりは、「労働環境の厳しさ」が一因であることは否めない。たとえば「学年主任」になった途端、ものすごい仕事量になる。成り手不足の昨今、5年目くらいからそうしたポジションに就き、仕事が回らなくなって病気休暇を取らざるを得なくなている人も少なからずいる。
ならば、最低限の教育技術と、それをバージョンアップしていく技量とを身につけた人材をどれだけ速く育てられるか?が重要になる。
だが今の研修システムでは無理だ。「指導書」に出ている授業をすることを強要される傾向が強い。「指導書」通りに授業できる教師がすばらしく、管理職や指導主事がそれを目指して競い合わさせていると言ったら言い過ぎだろうか?
なぜそうなってしまうのか?彼らが得ている「情報量」と「情報源」が限られているからだ。管理職や指導主事の仕事量を考えてみればわかる。仕事量が増えれば、入ってくる情報量は減る。
同じことは現場教師にも当てはまる。だから「もっと仕事量を減らせ!」と昔から多くの教師たちが言い続けてきているのだ。
ところがそんなことはお構いなし。「量」だけ増えている。
石の上に3年+2年のススメ
とは言え、選りすぐりの教育技術を知り、試し、身につけていくことを「石の上にも三年」続けていると、自信に変わってくる。そうなるとしめたものだ。何時間もかかっていた仕事や教材研究の「時間」がどんどん短縮される。その分、別の仕事に充てることができる。
余裕ができると「教師くらい楽しいものはない」と思えるようになる。
給料は安いのは否めない。しかし教師でなければ行くことがなかったような場所に、「仕事」としていくことができたり、保護者を含む多くの人と話をしたりすることを通して、「人前で話すこと」「指示を出して集団を動かすこと」は苦でなくなる。
また学生の頃と違い、「人間として成長している」という実感がもてるようになる。
そうなるまでには最低5年。ひたすら忍耐、辛抱の日々が続くかもしれないが、あとから振り返ってみれば、「やっててよかった」と思うだろう。
その日が来るまで、おそらく「追試」授業だけで乗り切れる。一つ授業を追試するたび、不安が自信に変わり、確信になる。「授業の百科事典」を活用できる今なら、それは十分可能だ。
学んだ事を追試、追試、追試。「授業通信」にまとめて発行する方法も追試してみよう。はこちらから。





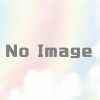


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません