道徳授業の定石化「いま、ぼくにできること」(2年東書)定石パターンで授業を組み立てる
あらすじ
2011年3月11日、町を大きな地震と津波が襲った。いろいろな物が一瞬でなくなった。水、食べ物、電気、家。当たり前だと思っていたものが、一瞬でなくなってしまった。がれきを片付けてくれた人。水を運んでくれた人。地震の時に一緒に泊まってくれた先生や友達。その時から僕の心の中は、「ありがとう」の気持ちであふれそうなくらい一杯になった。2週間ほどしてから修了式があった日。先生が「春休みの宿題は、一日に一回以上『ありがとう』と言われることです」と言った。(ぼくに何かできることはないだろうか)と考えて、避難生活を送る人のお手伝いをすることに決めた。
定石①「登場人物」「セリフ」「したこと」の確定
読み聞かせ後、「登場人物」確認。
ぼくが「したこと」を確認する。パワーポイントでテンポ良く進めるのもよい。キーワードにマスキングする際は、かくれている文字が薄く見えるように加工しておくと、スムーズに答えが返ってくる。
なぜそうするのか?道徳で扱う教材は初めて聞く話がほとんどだ。道徳では、国語のように時間をかけて何度も音読をし、内容読解する時間はない。とはいえ、子どもの学力差を考えるなら、話の内容を取り違えたり、勘違いの多い子も必ず存在する。そうした子たちのために行っていると考えればいい。あらすじを読み聞かせの前に伝えてから行うのも同じ理由だ。
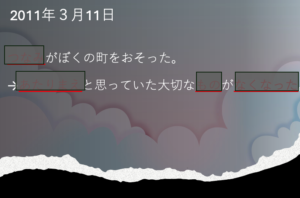
「登場人物」「セリフ」「人物評価」の確定
読み聞かせをしながら「登場人物」をマーカーで囲み、「セリフ」に番号を付けさせる。
次に発問①〜③で「人物評価」をする。
①「誰がいい人ですか?」
②「誰が一番だめ」
③「誰に問題がありますか?」
発問1 誰がいい人ですか?
①がれきを片付けてくれた人②水を運んでくれた人③先生④ともだちなどが挙がる。
「いい」理由を言わせると、「仕事で頼まれてやっているのではなく、自発的に行っている」という事に集約できる。
発問2 誰が一番だめですか。
この話で①〜④以外の人と言えば「ぼく」と「ひなんせいかつをおくる人」しかいない。
「ぼく」は避難所でお手伝いをしているのだから、「いい人」にあげる子もいる。それはそれでいいだろう。ただし、避難所で「お手伝い」をするまでは何もしていない。同じような小学生はたくさんいたはずだ。
「ひなんせいかつをおくる人」の中で、お年寄りや病気の人は何もできないのはやむを得ないとしても、がれきを片付けたり、水を運んでくれたりしていた人はいたはずなので、そうした人は「いい人」だ。
となれば、本文には書いてないけれども、「避難所で、何かできるのに何もしていない人」が「一番だめ」ということになる。
変換点の検討
発問3 ぼくはどこから変わったのですか。
先生から「ありがとう」の宿題が出されてから。
発問4 変わる前のぼくはどういう子でしたか。
ありがとうの気もちでいっぱいの子。(ぼくに何かできることはないだろうか)と考え、避難生活を送る人のお手伝いをすることに決めた子。
発問5 変わった後はどうですか。
お手伝いをし、いつの間にかみんなによろこばれるのが楽しくなった。
「自分」に返す
発問6 「お手伝い」をする時の自分は、どちらに近いですか。
発問7 これからの自分は、どうなりたいですか。
発問8 お手伝いをする時に、似たような体験はなかったか。
まとめ
「お手伝い」に関する教師の体験談がいいのでは?誰でも「お手伝い」にまつわる話は、何かしらあるのではないか?嫌々やっていたけど、だんだん楽しくなって、今でもお手伝いは楽しい、といった事を付け加えればいい。
最後に教科書の空いたスペースに授業の感想を書かせ、教科書を使った痕跡を残す。
モデリング・ナンバリング・ネーミング」誰でもできる討論授業2はこちらから
道徳授業の定石化 教材研究で悩まない!誰でもできる鉄板道徳授業についてはこちら
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません