道徳授業の定石化 「じぶんでオッケー」(東書2年)鉄板・定石展開で授業を組み立てる
鉄板授業展開を試す 
新しい学級での最初の道徳授業。二年生なので、道徳授業の趣意説明から入る。
「道徳の授業では、お話を読んで、「これは正しいことか、悪いことか?」考え、「今の自分はどうかな?」「これからはこうしたい。」ということを、みんなで意見を出し合って考えていきます。
①「善悪」の判断と、②「自分を振り返り、改善策を考える」
この二つで授業を進めていくことを伝えたなら、早速授業に入る。

道徳授業定石展開1⃣ 「登場人物」「セリフ」「人物評価」の確定
まずは登場人物やセリフにマーカーや番号を付ける「ナンバリング」作業をする。
鉛筆を一本出させ、読み聞かせながら、会話文に番号を付けさせていく。
指示1 (1行目)「おかあさん。ハンカチとって、早く、早く。」カギ括弧の上に①と書きます。
今は大型テレビに教科書をカメラで撮って映し出し、そこに書き込みをすることができるようになっているので、写し出してやってみせればいい。最初の授業なので、この辺りの作業は、丁寧に、一人一人隣同士で確認させながら進めていく。

続けて
(2行目)「しょうがないわね。はい。」この上に②と書いた人?優秀!
このように褒めて集中力を高め、
(3行目)「ハンカチ、オッケー。ちりがみ、オッケー。」③、書けた人?
(4行目)「そんなにいそいで…」④、書いた?
(5行目)「だいじょうぶ。」⑤
どんどん書き込ませるスピードを上げていく。もちろん、隣同士、キョロキョロ見合って、書けてなかったら「優しく教えてあげる。」と伝えて、教え合わせる。

登場人物は、とも子 お母さん 田中先生 みちえさんの4人だが、会話文に番号を付け終えたら、
①は誰のセリフ?(とも子)
と確認したら、①の上に「と」と、頭文字を書き込ませる。同様に「②は?」「③は?」とこれもテンポ良く確認と書き込み作業をさせていく。
ここまでが授業の下準備、ナンバリング作業だ。

次に発問①〜③で人物評価をする。
発問①「誰がいい人ですか?」
お母さん=手伝ってくれている。
発問②「誰が一番だめか?」
とも子=ハンカチをお母さんに取ってもらっている。
発問③「誰に問題がありますか?」
とも子=「わすれものをしない」と誓いを立てたけれど、自分でできることをお母さんに手伝ってもらっているのに、(わたしは、もうはじめちゃっているよ)と、言っている。
おかあさん=とも子にやらせればいいのに、手伝っている。
お母さんにも問題があると言えばあるの。意外と気が付かない子が多いのではなかろうか。出てこなければ、教えてやるのもいいだろう。

定石展開2⃣ 変換点の検討 
この教材は、定石発問がそのまま使える。
発問④「どこから変わった?」
「ともちゃん、すごい。いっしょにがんばろうね。」
「つぎの日のあさ」
この辺りから変わったことが言えればいいだろう。みちえさんに自慢してしまった手前、次の日の朝、自分でやらざるを得なくなったわけだ。
発問⑤「前はどう言えばいい?」
お母さん頼み。→そのことを平仮名三文字で?→◯◯◯んぼう(あまえんぼう)
発問⑥「後はどう言えばいい?」
自分でやれることは、じぶんでやっている→前よりも◯◯ちょう(せいちょう)する。
子どもから引き出したい言葉を、◯を使って考えさせ、引き出すのも大事な教育技術だ。
定石展開3⃣ 自分に返す 
定石発問⑦〜⑪がそのまま使える。
⑦「自分はどっちですか?」→成長しているか?と言われて、していると答えられない子もいるだろう。
⑧「今の自分は、前か後か?」→一年生の時と比べて成長していきたい、と思わせればいい。
⑨「これからどうなりたいのか?」→成長していきたい、と言わざるを得ない。
⑩「そういう体験はないか?」→二年生になって、何か始めたことがある子に言わせる。
⑪「そういうお話を知らないか?聞いたことがないか?」
道徳授業の最初の教材から、鉄板展開で安心して進められる。教材研究ほぼなしでもできる。
これは春から縁起がいい!
「モデリング・ナンバリング・ネーミング」誰でもできる討論授業2ついてはこちら
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ










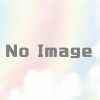
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません