「図画工作科」の授業技術 授業の百科事典を使って年間指導計画を作る。
年間指導計画を練る
教科書会社の年間指導計画を手に入れるのはとても簡単なのでここでは説明しない。入手したら、時数を確認する。低学年は2時間で完結する教材が多い。中学年以降は4時間、6時間と週をまたぐ教材が増えてくる。その間、制作途中の作品をどこに保管するのか?考えておく必要がある。
↓ヨッシーの学校で使っている図工教科書の指導計画

ヨッシーは今年、4年生の図工専科も担当。教科書が変更になったため、指導計画を作り直す必要があるため、教科書会社の指導計画をダウンロードした。ところが困ったことに「PDF」ファイルだったため、エクセルに落とし込めない。
試行錯誤の末、なんとか完成→4年図工指導計画
作ってみて改めて分かることがいくつかあった。
①年間授業時数は「60」時間。前期26時間、後期34時間で作成する。
②「絵画 工作 立体 造形遊び 鑑賞」の5項目に分けて指導計画を作る。
③5項目をバランス良く(「絵画、工作、立体」は前・後期に2つずつ。「造形、鑑賞」は1つずつ)配置する。
※絵画、工作、立体は、活動のゴール(作品完成)がある。造形は、子どもたちが何ができるかを考えて活動する。鑑賞は「思考、判断」が中心と思えるが、「知識」も必要だし、「主体的」に取り組んでもらわないといけないし…なかなかに難しい。
新年度、最初にやっておくべきこと
①「一括購入品」。必要な単元を調べ、「いつまでに発注するのか」確認すること。例えば「版画」関係の物品。版木、版画用紙、彫刻刀の注文時期など、学年会計担当の先生と打ち合わせておく。
②「身辺材料」が必要な教材は、1ヶ月前の学年便りなどで告知して集めておいてもらう。
③「教材キット」を教材屋さんに発注してもらわないといけない教材もある。4月最初に使う予定の教材見本を確保したら、すぐに作ってみること。値段が安く、作りやすいものがベストだ。
④備品、消耗品のチェックをし、新規購入、補充数などを確認する。図工主任なら、予算会議に向けての発注手続きの準備が入る。
授業の百科事典で教材研究
次は教材研究。「授業の百科事典」で「図工」「図画工作」「酒井式」などの言葉で検索し、次のようにリスト化しておく。
以下は「4年図工専科」用としてリストアップしたものだが、他学年での絵画指導でも使える内容だと思われる。冒頭の動画で紹介した「桜を描かせる」は、新年度、最初の2時間で扱いたい内容だ。「読書感想画」に取り組む場合、専科担当の場合は何時間で完成まで持っていくのかが大事だ。酒井式で取り組ませる場合、読み聞かせをしている時間はないので、たとえば3年国語で学習した「モチモチの木」を使う手がある。
絵画指導については「酒井式描画法」についての理解があった方がよりうまく指導できるかもしれないが、一度は「やってみる」ことをお勧めする。子どものつまずくところが予想できるようになるので、初任者であっても指導言に説得力が増し、自信をもって指導できるようになる。
| (図)スチレン版画、紙版画 |
| (図)手の描かせ方 |
| (図)動きのある人物 |
| (図)桜を描かせる |
| (図)絵の具の水入れ |
| (図)春の植物 |
| (図)人の逆さ顔 |
| (図)ヘビの絵を描こう |
| (図)パレットに名前を付ける |
| (図)自分の顔を描く |
| (図)お話の絵 |
※「工作」の指導技術については別の機会に。
前を覚える〜始業式までの最優先事項 子どもの名前を覚える効果は絶大だ はこちらから。
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ




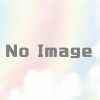


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません