追試は結果を保証する。指導書は病院食。成分表示は問題なくても、食べる気する?
絵に描いた餅はうまい?
「課題解決」「探究学習」「自由進度学習」という言葉が大流行りの令和教育界。
「またか‥」と思う。
ついこの間まで、「カリマネ」「単元を貫く」「アクティブラーニング」だと言ってたじゃないか。
子供達はそんな事に付き合わされる事を望んでいない。
わかりやすくて楽しい授業
①「もったいぶってないで、教わるべき事をさっさと教えてもらいたい。」
〜漢字や計算は必要だから、テストする日と計算の仕方をさっさと教えてほしい。
②「わかりやすくて、みんなで楽しく話し合える授業をしてほしい。」
〜ヒントがどこにも書かれてない問題を出して、グループで話し合って考えをまとめなさい、なんてこと無理。
①と②ができていれば、小学校で教わるべき大事なことの7割はカバーしている、と思う。
「スキル学習」&「討論の授業」ができる教師に
ところが、この二つを分かりにくく教える先生が少なくない。
①の「スキル学習」のやり方。これが分かれば、先生がいなくても覚えるまで繰り返し練習し、身に付けられるようになる。
漢字なら「目と耳と指」から同時入力。週に1回、10問ずつテストする。
まちがった漢字は練習してその日のうちに再テスト。
新出漢字が200字なのは3年と4年。
前期20週、後期20週と考えるなら、最初の10週で1回目のテスト。残り10週で2回目のテスト。2回目も同じ問題なら1回目よりもいい点数が取れる。
国語の毎時間10〜15分間は、漢字学習。
漢字学習の進め方を教えてくれて、ルーティンにしてくれれば苦痛じゃない。
一番困るのは、「宿題」にされてしまうこと。やらない子は永久に身につかない。家で宿題をやれない事情が子供にはあるのだ。
②の討論の学習は、最初からできるわけじゃない。
漢字学習を終えた残りの30分で教科書の音読がすらすらできるようになると、先生やみんなが考えて作った問題で「文章読解」学習をする。問題の答えは必ず文章のどこかに答えが書かれている問題を作る。
作るのが簡単なのは「穴埋め」問題。文章から答えを見つけてそっくりそのまま抜き書きすればいいという問題。「誰」が「どうした」や、「いつ」「どこで」を見つけて「◯文字」で答える問題も簡単に作れる。
選択肢を作って「どれが正しいですか。」「ダメなのはどれですか。」「番号で答えなさい」という問題になると少しレベルアップ。
一人一台端末があるから、問題を大きく読みやすい文字で書いた紙を写真で撮って送り、みんなで共有うし、自分のペースで答えていく。問題を一つ作ると5点。答えると2点。自分が何点取れたかを計算して提出する。
こういうふうに学習が進んでくるといよいよ「討論」の学習だ。みんなが作った問題から先生が選んだり、答えがはっきりしなくて微妙な問題について話し合う。
最初は四人グループで話し合う。班で意見が纏まれば、代表一人が黒板の前に出てきて発表する。みんな意見が違ったら四人が出て発表。
発表が終わったら質問タイム。「〇〇さんの意見は、こういうことなんですか?」と確かめるのが一番いい。
そしていよいよ「討論」タイム。
「〇〇さんの意見も分かるんですが、私は〜と考えます。国語辞典を見ると、〜と書いてあるので、〜と考えるからです。」
発表の仕方も教える。相手が反論したかったら1回だけできる。それに対しての反論は、ノートに書いて提出することになっている。
討論の結論は出なくていい。でも自分の考えは最後にまとめて書いて提出する。これに一番時間がかかるけど、相手の意見と自分の意見をそれぞれ50文字ずつ、合計100文字でまとめて、最後に自分の考えを書くのが面白い。成績を良くしたければ「どれだけ書いたか。」という量を見て先生はつけていると言っていたから、最後まで頑張って書く。
「計算」も同じ。計算手順を唱えながら問題を解いてみる。やり方が分かったら、2分で2問、5問、10問、どこまで解くことができるか試してみる。
①も②も指導書にはこうした技術について詳しく書いている箇所はない。
例えば「漢字」を効果的に身に付ける学習方法を書いたページ。見たことがない。それが◯万円もする値段で、日本全国、各学校予算のかなりの金額を使って備えられている。「驚き!」としか言いようがない。
「討論」の仕方もしかり。それっぽいことが書いてあっても、実は絵に描いた餅。簡単じゃない。指導書通りにやってみればすぐ分かる。そうならない。指導書の原稿を書いている先生と自分と比べたら分かる。力が全然違う。初任者にもできるように書かれていない。
追試報告は書かれた事に責任を持って発表されている
何万円もする指導書とは比べられないくらいの低価格設定になっているのが、教育界における「追試論文」だ。T-TUBER動画サイト然り。ヨッシーのこのサイト然り。TOSS LANDは言うまでもない。読むだけなら0円。これらはすべて無料で提供されている追試報告の塊と言っていい。
ただし実際に追試してみないことには、指導書以上に効果がある指導法なのかどうかはわからない。とは言え、先行実践を踏まえた追試かどうかは、記載されている引用文献などを見れば分かるので、そうした報告は一定の効果があると考えられよう。
数万円出して、誰にでも効果があると保証されていない指導例が書かれている指導書の指導を選択するか、初任者にも「授業の選択肢」を提供するサイト情報をとるかは、教師に認められた裁量権だ。研究授業では「指導書の指導計画をもとに考えました」と言うセリフが免罪符になっているようなところもあるのは否めない。それはそれとして、日々の授業を研究授業のように行うことは無理がある。
初任者にも「授業の選択肢」を!その声に応えられるサイトでありたい。
成績処理は「技術」の問題はこちらから
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ





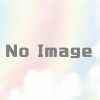
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません