道徳授業の定石化「とおるさんのゆめ」(教出2年)よいところをのばす
長文教材の扱い方
「とおるさんのゆめ」は、二年生の後半に配当されている4ページの教材。これだけ長文だと「聴覚入力が苦手」な子は、一回の読み聞かせで内容を正しく把握することはとても難しい。
そうした子も安心して話を聞けるようにするためには、読み聞かせの前に「あらすじ」を伝えてから読んでいく事が大事だ。そして、話の途中途中で
「誰が出てきた?」(ぼく)→「鉛筆で丸囲み」
「次は?」(とおるさん)「赤鉛筆で」
「これは誰が言ってる?」(とおるさん)「①とおるさんのセリフ、赤線引く」
「とおるさん、どんな子?どんなことしてる?」(おとなしい)(あそびにさそってもあそばない)
といった発問や指示を出しながら「登場人物」「セリフ」「したこと・特徴」などを記述を元に確認していく必要がある。
ワークシートの設問は意欲を高めるているか?
教科書指導書には、ワークシートが付いているものが多い。これを「使わなければいけない」という法的義務など全くないにも関わらず、手間ひまかけてこれを印刷し、ありとあらゆる授業に利用している教師が想像以上に多い。ワークシートには、いい物もたしかにある。しかし、その中身は妥当なのか?
「とおるさんのゆめ」のワークシート設問を書き出してみた。(※ワークシートには、イ〜二の記号は書かれていない。)
イ「みんなが話したとおるさんのよいところを聞いて、「ぼく」がおどろいていたのはどうしてでしょう。」
ロ「みんなはどのような気もちで、とおるさんの話にはくしゅをしたのでしょう。」
ハ「友だちのよいところを見つけて、おたがいのよいところをつたえ合いましょう。」
二「友だちのいけんを聞いて、気づいたことや考えたことを書きましょう。」
国語の時間に短作文課題を出され、一文字も書けずに机に突っ伏してしまう子が少なくない。そういう子が、これらの設問に短時間で考えを書けるはずがない。
そうした事を知っている教師は、ワークシートに何も書けない子を見て、どうしているのか?なぜそれを使い続けているのか?なぜ初任者に使うよう勧めるのか?不思議で仕方ない。(閑話休題)
イ「おどろいていたのはどうしてでしょう。」
そんなこと分かりません。文中にその答えは書かれていない。強いて言うなら、「どうぶつにやさしい」という「やさしい」という言葉に反応して「おどろいていた」と推測できるかもしれないが、そんなことはどうでもいいことだ。
※そもそも、「おどろいていたぼく」という表現も変。
「おどろいたぼく」と書かれていれば、「やさしい」という記述が直前にあるので、それに反応して「おどろいた」のだろうと読み取れるが、そうなっていない。
「おどろいていたぼく」では、みんながとおるさんが「毎日、しいくごやに行って、どうぶつのせわをしてい」たり、「かたずけたり」しているなど、僕が知らなかったとおるさんのいいところを発表しているのを聞きながら「おどろいていた」とも読み取れる。
一方で、とおるさんは「どうぶつにやさしい」だけじゃない。「このあいだも、ぼくのおとしものをいっしょにさがしてくれた」し、「こまっている人がいると、すいぐにたすけてくれる」し、とおるさんとの出来事を思い出してあれこれと考えていた、というような読み取りもできる。
こうしたことは国語でやればいい。道徳の授業で考えさせるような内容ではない。
ロ「みんなはどのような気もちで、とおるさんの話にはくしゅをしたのでしょう。」
これも答えようがない設問だ。
A「ありがとう」と言ったから?
B「あまりみんなとあそべなくて、ごめんね」と謝ったから?
C「大人になったら、どうぶつ園のしいくいんさんになりたいです。」と夢を語ったから?
D誰かが発表したら、反射的に拍手することになっているから?
自然なのはD。でも、この設問はそんな答えを期待しているわけではなかろう。
となると、AかBかCに近い意見を発表した子に対して、
「なるほど。そういうことはありますね。」
すべての発表が追認されていくような授業にならざるをない。
ちなみに、A、B、Cのようなことを、短時間でワークシートに書き込む作業は、普段から考えを書き慣れていない子にとっては苦行でしかない。となると、道徳の時間に活躍する子と言うのは、自分の考えを短時間にまとめて書き、Dのような本音ではなく、A、B、Cのような建前の答えを発表してくれるお利口さん、ということにならざるを得ない。
だから道徳授業はつまらない。
だから定石①〜③で授業を進めた方がまだまし!
あらすじ
僕のクラスでは、朝の会や帰りの会に「ともだちのよいところ」を伝える時間がある。今日は「とおるさん」のよいところを伝える日だった。ところが、とおるさんと僕はあまり遊んだことがない。僕は、みんなの発表を聞きながら、どんなことを伝えたのでしょう。
定石①「登場人物」「会話文」「したこと」の確定
「登場人物」→とおるさん(赤丸囲み) ぼく(青丸囲み) みんな
出だしから「ぼく」の目線で語られているが、「とおるさん」と書かれている箇所が最初見開き2ページで8カ所と圧倒的に多いので、とおるさんが「中心人物」である。しかも題名は「とおるさんのゆめ」となっている。
「会話文」は6つ。ナンバリングをして、話主も確定する。
ぼく⑤ とおるさん①⑥ みんな②③④
発問1「とおるさんのよい所は何か?」
A どうぶつのせわ
B ウサギの水替えや糞の片付けを頑張る
C どうぶつにやさしい
D こまっている人をすぐたすけてくれる
定石②変換点の検討
さて、この後、定石発問の中からどれを使うか?
本教材は長文ということもあり、会話文が6つ出てくる。授業定石①でそれらに①〜⑥までナンバリングをしているので、「一番大事な言葉」を見つけさせる。
発問2「①〜⑥の中で、一番大事な言葉は何番か。」
⑤番→動物だけでなく、僕たちにもいつも優しい。
⑥番→あそびに誘ってくれた友だちとあそばなかったことをあやまっている+「とおるさん」が大人になった時の夢を話している。
子どもたちの意見が⑥番に集約するとすれば、「とおるさんのゆめ」という教材名の中にある「ゆめ」と繋がり、本教材の主題「よさを伸ばす」「個性の伸長」にジャストミートしていく。
そうなれば、あとは発問3へと無理なく繋げていくことができる。
定石③今の自分、未来の自分を選ぶ
発問3「今の自分は、夢をもっている「とおるさん」に近い(似ている)か。」
つまりは、「将来の夢があるか?」「夢に向かって生活しているか?」ということだ。
発問4「これからの自分は、どうなりたいか。」
→自分のよさを活かしていきたい。ほめられた所や良いところを伸ばしていきたい。夢に向かってがんばりたい。
まとめ
1月からの生活科学習では、小さい頃からの成長の記録をまとめる学習が始まる。本教材はそれと時期が重なる。生活科の教科書(光村)には、「友達同士、良いところを伝え合おう」という活動が示されている。
二年生の発達段階を考えると、自分に対して過剰に自信をもちすぎ、時に他者に対して厳しく当たったり、逆に自己評価がとても低く、友だち関係が築きにくく悩んでいる子も少なからずいる。
そうした中で、「他者からの評価」という第三者からの「客観的視点」も取り入れ、この時期の子どもたちの可能性を伸ばしていきたいという意図が、どこの教科書会社の編集者にあるのだろう。
「生活科の学習で、自分の成長の記録をまとめます。その中に友達同士で「いいところをつたえあおう」という活動があります。友達の良い所を見つけ、知らせてあげるといいかもしれませんね。」
押しつけにならないように気を付けながら、こんなようにまとめるのもいいかもしれない。
道徳授業の定石化「七つのほし」はこちらから。
道徳授業の定石化「①登場人物の確定」「②変換点の検討」「③今と未来の選択」についてはこちらから。
最新版【授業の百科事典】リンク集データの入手は【ヨッシー’s STORE】へ




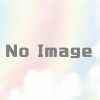



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません